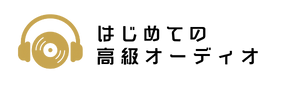はじめまして! 当ブログ「はじめての高級オーディオ」の管理人の「かんりにん」と申します。
数あるオーディオサイトの中から、当ブログにお越しいただき、本当にありがとうございます。
このページでは、私がどんな人間で、どんな想いでこのブログを書いているのか、そして「ポータブルオーディオ沼」にすっかりハマった私が、今、憧れの「据え置き高級オーディオ」に挑戦していく、その奮闘記についてお話しさせてください。
このブログの現在地:読者の皆さんと共に楽しむということ
まず、正直にお伝えしたいことがあります。 私は、据え置きの高級オーディオに関しては、皆さんと同じ「初心者」です。
「え、初心者が書いているブログなの?」
そう思われるかもしれません。ただ、私には10年以上、趣味として夢中になってきた世界があります。それが「ポータブルオーディオ」の世界です。
もちろん、技術的な知識を持つ専門家というわけでは全くありません。 あくまで趣味として、色々なイヤホンやプレーヤーを聴き比べて「こっちの音のほうが好きだな」と楽しんできただけです。
このブログは、そんな僕が「憧れの据え置きオーディオに挑戦したらどうなるんだろう?」という、ごく個人的な探求の記録です。
専門家ではないからこそ、皆さんと同じ初心者の目線で、情報を集め、悩み、時には失敗もしながら、その過程で見つけた感動や楽しさを共有していきたい。このブログを、皆さんと一緒に最高のオーディオ環境を夢見て、その道のりを楽しんでいく場所にしたいと思っています。
始まりは父のミニコンポ

私のオーディオへの情熱の原点は、小学生の頃に遡ります。 実家のリビングには、父が大学生の時に買ったという90年代のケンウッド製ミニコンポ「ROXY L3」が鎮座していました。当時の私にとってはラジカセが当たり前。そこから流れるクリアで迫力のある音、そしてメカニカルで男心をくすぐるデザインに、子供ながら「なんだこれ、すごい!かっこいい!」と強烈に惹きつけられたのを、今でも鮮明に覚えています。
中学生になり、自分の部屋にどうしてもオーディオが欲しくて、誕生日プレゼントにパイオニアのミニコンポを買ってもらいました。嬉しくて毎日音楽を聴き、しまいにはハードオフでジャンク品のサブウーファーを見つけてきて、自己流で接続して喜んでいました(笑)。この頃から、音への探求心と、自分で何かを試す楽しさに目覚めていたのだと思います。
ポータブルオーディオ沼にハマるまで
高校生になり電車通学が始まると、私の興味は自然とポータブルオーディオへと移っていきます。 お年玉を握りしめてウォークマンのAシリーズ(NW-A865)を手に入れ、イヤホンには少し背伸びをしてオーディオテクニカの「ATH-IM01」を選びました。

当時購入した時のパッケージ
BAドライバー1基ならではの繊細でクリアな音。ダイナミックドライバーの安価なイヤホンとは明らかに違う、全音域のつながりの良さ。その違いを自分の耳で理解できた時の満足感は、私をオーディオという深い沼に引きずり込むのに十分すぎるものでした。
大学時代には、一度据え置きオーディオに挑戦したこともあります。バイト代で中古のマランツ製プリメインアンプを、ハードオフで古いオンキョーのスピーカーを手に入れ、アパートの一室で鳴らしていました。しかし、隣人への音漏れの心配や、あまりにも奥深く、そして高級な世界に「これは本格的にのめり込むと大変なことになる…」と、ある種の恐れを感じてしまったのです。
そこから、私は再びポータブルオーディオの世界に没頭していきます。 eイヤホンに行けば3時間以上試聴に没頭し、気づけば手元にはEmpireEarsの「Valkyrie」とCaiynの「N5iiS」が…。最高のポータブル環境で音楽に浸る日々は、至福そのものでした。(Valkyrieは金欠の際に泣く泣く手放してしまいましたが、今でも心から後悔しています…)

そして今、据え置きオーディオへの再挑戦
社会人となった現在の私の愛機は、Hiby R6 IIIとUniqueMelodyのMaslowです。 そして、我が家のリビングには、パイオニアのAVアンプ(VSA-820)を中心とした5chサラウンドシステムがあり、休日にライブ音源を臨場感たっぷりに楽しむのがささやかな幸せです。

ポータブルで最高の音を追求し、リビングではサラウンドで音楽に包まれる。そんな充実したオーディオライフを送る中で、あの子供の頃に感じた「憧れ」が、再び大きくなっていることに気づきました。
「いつか、最高のオーディオ環境を構築できる家に住み、心ゆくまで音楽と向き合いたい」
このブログは、そんな私の夢を実現するための第一歩です。 ポータブルオーディオで培ってきた「音を楽しむ気持ち」を大切に、憧れの据え置きオーディオという世界を、皆さんと一緒に手探りで楽しんでいきたいと思っています。
この試行錯誤の先に、どんな音が待っているのか。 ぜひ、あなたも一緒に、その感動を分かち合う仲間になってください。
かんりにん